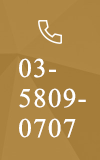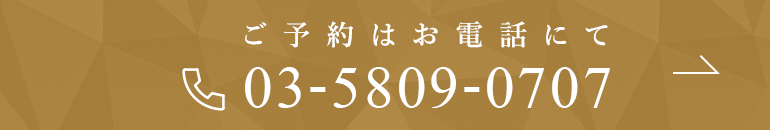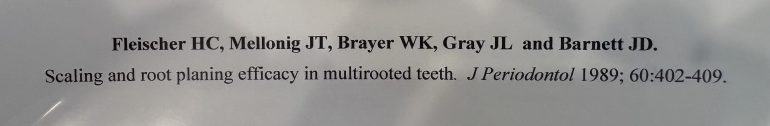
Fleischer HC, Mellonig JT, Brayer WK, Gray JL and Barnett JD.
Scaling and root planing efficacy in multirooted teeth. J Periodontol 1989; 60:402-409.
この研究では、
抜歯予定の奥歯(大臼歯)に対して行われました。歯周外科を行って歯茎の深いところの歯石を除去したグループと歯周外科を行わずに歯茎の深いところの歯石を除去したグループで歯石の取り残しを確認しました。
今回の研究で選ばれた歯は大臼歯という大きな奥歯です。大臼歯は根っこが複数あり、根っこの間の歯石は取りにくい、そもそも奥歯で器具も到達しにくい部位であるという難しい歯に対しての治療方法を検証したものです。
結果、浅い歯周ポケット(3mm以下)であれば歯石の除去率に違いはなかった。
4mmを超える部位については
歯周外科を行った方が良好な結果が認められた。
歯の根の間の部分は歯周外科を行っても、歯石の取り残しがあった。
歯石の取り残しはセメントエナメル境、根の陥凹部、ラインアングルに多く認められた。
歯周病の治療として、歯茎の深いところの歯石の除去はとても基本的な処置ですが、奥歯(特に大臼歯)には“歯石が取りにくい場所”が多くあります。
その代表が「分岐部」と呼ばれる、歯の根が枝分かれしている部分です。今回は、そのような難しい場所に対して、外科処置と非外科処置でどれだけ歯石が取れるかを調べた研究をご紹介しました。
この研究を通して改めて感じたのは、分岐部や根のくぼみなど、複雑な形をした場所では、外科処置を行い直接目で見ながら丁寧に処置をしても、どうしても歯石が残ってしまうという現実です。
特に深い歯周ポケットでは、器具が届かない・見えないという限界があり、たとえ熟練の歯科医師でも完全に取り除くことは難しいことがわかっています。
「しっかり処置しても治らない部分がある」というのは、がっかりされるかもしれません。
けれど私は、その限界を正直に伝えたうえで、どこまで回復が見込めるのか、どう付き合っていくのかを一緒に考えることが、治療以上に大切だと思っています。
ひのまる歯科では、大臼歯の分岐部や深い歯周ポケットに対しては、非外科で対応できる範囲と、外科処置が必要な範囲を見極めて治療方針をご提案しています。
ただし、どんなに治療の腕がよくても、完全な歯石除去が難しい部位があることもお伝えしています。
「どこまできれいにできるか」だけでなく、「残ったリスクをどう管理するか」までが、本当に意味のある歯周治療だと考えています。
千駄木近隣にて、お口の健康や歯周病について不安なこと、気になることがある方は是非一度ご連絡ください。