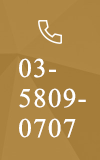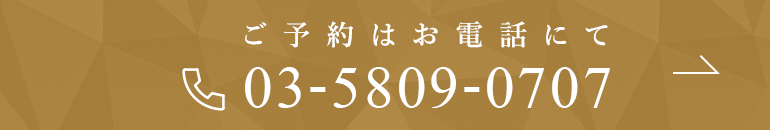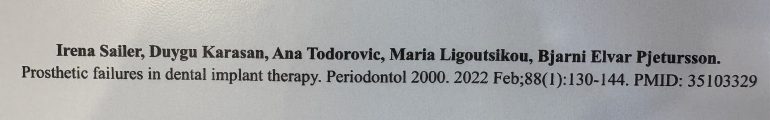
Irena Sailer, Duygu Karasan, Ana Todorovic, Maria Ligoutsikou, Bjarni Elvar Pjetursson.
Prosthetic failures in dental implant therapy. Periodontol 2000. 2022 Feb;88(1):130-144. PMID: 35103329
インプラント治療において、手術だけでなくその上に取り付ける被せ物(補綴物)の設計や素材選びは、治療の長期安定性に大きな影響を与えます。とくに「インプラント補綴設計」を正しく行うことで、将来的なトラブルの発生率を大きく下げることが可能です。
今回は、世界的な研究やレビュー論文をもとに、よくある補綴トラブルの傾向と、それを防ぐための設計・材料の考え方を紹介します。
インプラントをご検討中の方にとっても、参考になる内容です。
【よくあるトラブルとその発生率】
インプラントに取り付ける補綴物では、次のような技術的なトラブルがよく見られます。
まず代表的なのが、スクリューのゆるみや破折です。補綴物とインプラントを固定するネジが緩むことがあり、過去の研究では5年間で8.8%という報告もあります。スクリューが複数ある場合や角度調整型のインプラントでは、リスクがやや高まる傾向にあります。
次に多いのは被せ物の脱離です。特にセメントで固定した場合、使用する素材や接着剤の選び方次第で、脱離のリスクに差が出ます。近年ではレジンセメントの普及により、オールセラミッククラウンの脱離は減少傾向にあります。
また、インプラント補綴特有のトラブルとして、セラミック部分のチッピング(欠け)が挙げられます。とくにジルコニアに陶材を焼き付けたタイプは、強度の点で不安が残ることがあり、チッピング率が他の素材に比べて高いとする研究もあります。
【素材ごとの特徴と選び方】
メタルセラミック(いわゆる金属焼付けセラミック)は、昔から使われている信頼性の高い素材です。フレームが金属なので強度が高く、5年での脱離やチッピングも比較的少ないという特徴があります。
一方で、審美性を求めてジルコニア インプラントクラウンを選ぶ患者さんも増えています。ジルコニアは見た目が自然で金属アレルギーの心配が少ない一方、前装材のチッピングやフレームの破折リスクが高いという報告もあります。
最近では、モノリシックジルコニアやモノリシック二ケイ酸リチウムといった「前装なし」の一体成型クラウンが注目されています。チッピングのリスクが少ない反面、現時点では中長期のデータが限られているのが課題です。
【連結するか、単独で仕上げるか】
隣同士のインプラントを「連結(スプリント)」にするか、「非連結(単独クラウン)」にするかは、症例ごとに選択する必要があります。
例えば、骨が弱い、噛む力が強い、治療費を抑えたいというケースでは、2本のインプラントで3本分のブリッジ(インプラント支持ブリッジ)にすることで、コストとトラブルの両面で安定した成績が得られることがわかっています。
一方で、清掃性やトラブル時の対応のしやすさを重視する場合は、1本ずつクラウンを装着する「非連結」の方が有利です。ただし、セメントの残りかすが周囲の炎症を引き起こすリスクがあるため、徹底した管理が必要です。
【アバットメントの高さと骨吸収】
インプラントと被せ物の間をつなぐ「アバットメント」の高さも、骨の減りに影響することがあります。
1mmのアバットメントよりも3mmのアバットメントを使ったほうが、インプラント周囲の骨吸収が少なかったという報告もあり、歯肉が薄い方には特に高さのあるアバットメントの使用が推奨されることがあります。
【インプラント治療を検討される方へ】
インプラントは手術だけでなく、被せ物の設計や材料の選び方によって、10年後の結果が大きく変わります。
ひのまる歯科では、どのような設計が最適かをわかりやすくご説明し、安心して治療に進めるようサポートいたします。
気になることがあれば、お気軽にご相談ください。