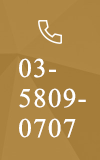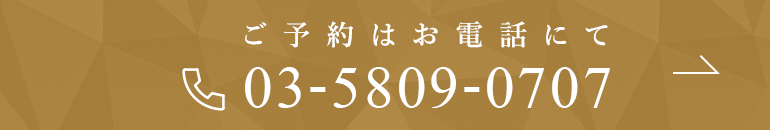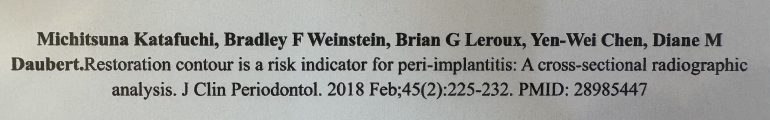
Michitsuna Katafuchi, Bradley F Weinstein, Brian G Leroux, Yen-Wei Chen, Diane M
Daubert.Restoration contour is a risk indicator for peri-implantitis: A cross-sectional radiographic
analysis. J Clin Periodontol. 2018 Feb;45(2):225-232. PMID: 28985447
〜インプラント周囲炎と修復物の角度の深い関係〜
「インプラントを入れたけれど、将来のトラブルが心配」
「見た目が自然なインプラントがいいけれど、メンテナンスもしやすい方がいい」
そんなお悩みをお持ちの方へ。
今回は、インプラントの形(特に歯ぐきから出る部分の角度やふくらみ)と炎症リスクとの関係について、最新の研究をわかりやすくご紹介します。
【インプラント周囲炎とは?】
「インプラント周囲炎」は、インプラントの周りの骨や歯ぐきに起きる慢性的な炎症です。進行すると、せっかく埋めたインプラントがグラグラになり、最悪の場合は撤去しなければならなくなることもあります。
千駄木近隣でも、メンテナンスが不十分だったり、設計に無理があったりして、トラブルに悩まれる方が少なくありません。
【角度が30度を超えるとリスクが倍増】
今回ご紹介する研究では、修復物の「エマージェンスアングル(歯ぐきから出てくる角度)」に注目しました。
研究では、平均10年以上の経過を見たインプラントを対象に、X線で修復物の形と炎症の有無を調べた結果、
・角度が30度を超える場合:周囲炎の発生率 31.3%
・角度が30度以下の場合:発生率 15.1%
という、明らかな差が確認されました。
つまり、インプラントの立ち上がり部分の角度が急であればあるほど、歯ぐきに負担がかかり、炎症が起きやすくなるということがわかります。
【「ふくらみ」もリスクになる】
さらに、歯ぐきから出てくる部分の形が「凸状(ふくらんでいる)」だと、そのリスクがより高くなることも示されました。
特に「角度が30度を超え、かつ形が凸状」の場合、インプラント周囲炎の発生率は37.8%にも上ります。
これは、歯ブラシが届きにくくなったり、歯ぐきに圧力がかかりすぎることが原因と考えられています。
【ティッシュレベル型では影響が少ない?】
なお、すべてのインプラントが同じように影響を受けるわけではありません。
インプラントには「ボーンレベル型」と「ティッシュレベル型」がありますが、今回の研究では、ティッシュレベル型では角度や形状との関連性はほとんど見られませんでした。
つまり、設計や埋入位置によってはリスクをコントロールできる可能性もあります。
【インプラント周囲炎 リスクを減らすには】
インプラントのトラブルを防ぐためには、以下のポイントが重要です。
・エマージェンスアングルは30度以下を目安に設計
・修復物はできるだけ凸状を避け、清掃しやすい形に
・自宅でのブラッシングと定期的なメンテナンスの両立
また、最初の設計段階でどのようなインプラントを使い、どんな角度で立ち上げるかは、歯科医師の経験と技術に大きく依存します。
【ひのまる歯科では】
ひのまる歯科では、インプラント周囲炎のリスクを最小限に抑えられる設計を重視しています。
ただ見た目が良いだけでなく、清掃性とメンテナンス性を備えたインプラントの形を、一人ひとりに合わせてご提案しています。
今あるインプラントに不安をお持ちの方、これから治療をご検討の方も、お気軽にご相談ください。