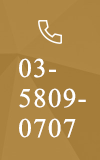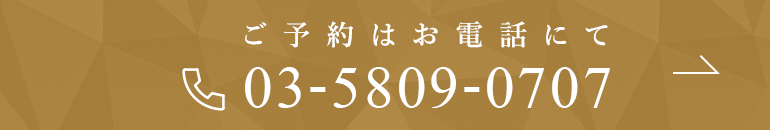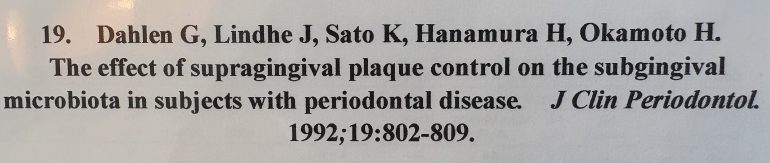
Dahlen G, Lindhe J, Sato K, Hanamura H, Okamoto H.
The effect of supragingival plaque control on the subgingival
microbiota in subjects with periodontal disease. J Clin Periodontol.
1992;19:802-809.
「毎日きちんと歯みがきしてるのに、歯ぐきの腫れがよくならない」
「歯の表面はキレイだけど、歯ぐきの中はどうなっているの?」
そんな疑問を持つ方は少なくありません。
実は、歯ぐきの中(歯肉縁下)にいる細菌が、歯周病の進行に大きく関わっています。では、その細菌を減らすにはどうすればいいのでしょうか?
今回は、歯みがきやスケーリングなど「縁上(歯ぐきの上)のケア」だけで、歯ぐきの中の菌にまで影響があるのかを調べた興味深い研究をご紹介します。
徹底した歯みがきで歯ぐきの中の菌が減った
スウェーデンと日本の共同研究チームは、軽度から中等度の歯周病患者300人を対象に、歯ぐきの上のプラークを徹底して除去するケアを行いました。
・歯科衛生士による歯みがき指導
・歯ぐきの上のスケーリング(縁上スケーリング)
・定期的なモニタリング(3か月で4〜8回)
このプログラムを2年間続けたところ、次のような結果が出ました。
歯ぐきの出血や菌が大幅に減少
・プラークの割合は60%から15%に減少
・出血の割合(BOP)は40%近くから5%に減少
・深い歯周ポケット(6mm以上)は、平均で5.4mmまで改善
・歯周病の原因菌(P.gingivalisなど)は、浅い部分でも深い部分でも大きく減少
つまり、歯ぐきの表面をキレイに保つことで、内側の菌にも影響を与え、改善が見られたということです。
ポイントは「継続」と「精度の高いケア」
この研究では、特別な薬や外科処置は行われていません。
それでも歯ぐきの健康が改善した理由は、以下のような要因が考えられます。
・歯ぐきの表面にプラーク(細菌の塊)を残さないことで、炎症が鎮まり、細菌が増えにくくなった
・歯みがきやスケーリングを「定期的」に行い、「自己流で終わらせなかった」ことが大きな効果につながった
千駄木で歯周病に悩む方へ:家庭のケアとプロのケアの両立を
ひのまる歯科では、歯周病予防や治療において、患者さまご自身の丁寧な歯みがき習慣と、歯科衛生士による定期的なケアを両輪として支えています。
歯周ポケットの深さや出血、歯ぐきの中の菌の状態を診ながら、状態に合わせたクリーニングや生活指導を行っています。
「歯みがきだけでは不安」という方へ
「ちゃんと磨けているか心配」
「最近、歯ぐきが腫れやすい」
「歯医者でちゃんと診てもらいたい」
ひのまる歯科では、痛みに配慮した診療とマイクロスコープを用いた診査・診断で、将来を見据えた予防と治療をご提案しています。
まとめ
・歯ぐきの上を清潔に保つことは、内側の菌にも大きな影響を与える
・プラークを減らすことで、出血や炎症が大幅に改善される
・家庭でのケアに加えて、歯科医院での定期的なクリーニングが効果的
10年後、20年後も自分の歯でしっかり噛んで食べられるように。
千駄木のひのまる歯科が、あなたのお口の健康を全力でサポートします。